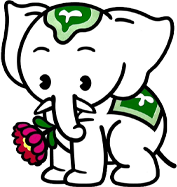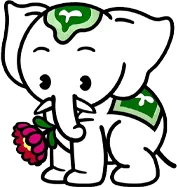葬儀の日の照と日取り選びで知っておきたい六曜やマナーのポイント
2025/11/09
葬儀の日の照や日取りで迷われていませんか?大切な故人を見送る場面では、六曜や友引といった「日の良し悪し」が気になる一方で、親族のスケジュール調整や火葬場の空き状況など現実的な問題も絡み合います。細やかなマナーや地域の風習を踏まえ、どのようにバランスよく葬儀の日程を決めるか——本記事では、葬儀における日の照や六曜の基礎知識、日取り決定の注意点や押さえておきたいマナー、実際の調整事例までを徹底解説します。読了後には、急なお別れにも落ち着いて臨み、家族や関係者が納得できる葬儀の日取り選びができる自信が得られるはずです。
目次
葬儀の日の照は六曜をどう考えるべきか

葬儀の日の照と六曜の基本知識を解説
葬儀の日取りを考える際、多くの方が気にされるのが「日の照」や「六曜」といった暦の考え方です。六曜は先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の6種があり、それぞれに吉凶があるとされ、葬儀の予定を立てる際にも参考にされることが一般的です。
特に「友引」は「友を引く」とされ、葬儀を避ける風習が根強く残っていますが、地域や宗教、家族の考え方によって対応は異なります。現代では火葬場や式場の空き状況、親族や参列者のスケジュールも大きな要素となっており、六曜だけでなく現実的な事情も重視されるようになっています。
また、六曜はカレンダーに記載されていることが多く、葬儀日程表の作成や日取り決定時にも確認されることが一般的です。こうした基礎知識をもとに、遺族や関係者が納得できる日程選びを心がけることが大切です。

六曜で見る葬儀の日柄選びのポイント
六曜の中でも、葬儀に適しているとされるのは「仏滅」や「大安」、控えた方がよいとされるのは「友引」です。仏滅は「すべてが終わる日」とされるため、忌み事に適していると考えられ、葬儀の日として選ばれることが多いです。
一方、友引は「友を引く」という語感から、友人や親族まで不幸が及ぶという意味合いで避けられる傾向にあります。実際に多くの火葬場が友引を休業日としている場合もありますので、日取りを決める際は事前の確認が必要です。
ただし、六曜を重視するかどうかは遺族や地域の考え方によります。例えば、仕事や学校の都合、遠方からの参列者の配慮など、現実的な事情を優先するケースも増えており、柔軟な対応が求められます。

友引や仏滅など葬儀における日の考え方
葬儀の日取りで特に意識される「友引」は、「友を引く」という意味合いから、葬儀を避けるべき日とされています。多くの地域や火葬場でも友引は休業日となっている場合があり、実質的に葬儀が行えないことも少なくありません。
一方で、「仏滅」は六曜の中で最も縁起が悪いとされますが、「すべてが終わる日」という意味合いから、葬儀には適していると考えられています。また、「大安」は全てにおいて吉の日とされ、日取りに迷った際の選択肢となることもあります。
しかし、こうした六曜の考え方はあくまで一つの目安であり、最近では火葬場の予約状況や家族の都合を優先するケースも増えています。地域や宗教、遺族の意向によって柔軟に判断することが重要です。

葬儀日取りに六曜が与える影響と実例
六曜は葬儀日程の決定に少なからず影響を与えています。たとえば、友引は火葬場が休みとなることが多いため、自然と他の日に葬儀をずらす必要が出てきます。実際、火葬場や式場の予約状況を確認した結果、六曜の影響で希望日が取れないこともあります。
一方、仏滅や大安は比較的予約が取りやすい場合もあり、参列者や遺族の都合に合わせて日程調整を行うことが可能です。特に遠方からの親族の参加や、仕事・学校の関係で特定の日にしか集まれない場合には、六曜よりも現実的なスケジュールを優先することが一般的です。
近年では六曜をあまり気にしない方も増え、都合の良い日で葬儀を執り行うケースも多く見受けられます。六曜による制約がある場合は、早めに相談・確認を行い、トラブルを未然に防ぐことが大切です。

六曜を参考にした葬儀の日程調整のコツ
六曜を意識した葬儀の日程調整では、まずカレンダーで六曜を確認し、友引を避けることが基本となります。そのうえで火葬場や会場の空き状況、僧侶や参列者のスケジュールを早めに調整することが重要です。
地域や宗教によっては六曜をまったく気にしない場合もありますので、遺族や関係者と十分に話し合い、納得のいく日程を決めることが大切です。特に平日や仏滅などは予約が取りやすいことも多く、柔軟に対応することでスムーズな進行が可能となります。
六曜だけにとらわれず、実際の事情を総合的に判断することが失敗を防ぐポイントです。万一、希望日が取れない場合も慌てず、家族や関係者と相談しながら最適な日程を模索しましょう。
大切な葬儀日取り選びの基本と注意点

葬儀日取り決定の基本手順と流れを紹介
葬儀の日取りを決める際は、まずご遺族や親族の都合、火葬場や僧侶のスケジュール、そして地域の風習を総合的に考慮する必要があります。一般的な流れとしては、逝去後すぐに葬儀社へ連絡し、ご遺体の安置を行った後、通夜と葬儀の日程を調整していきます。特に火葬場の予約状況は日程決定に大きく影響するため、早めの確認が重要です。
日程決定後は、親族や関係者への連絡、僧侶や地域の代表者との調整を行い、必要な準備や手続きも進めます。葬儀日程の流れを把握しておくことで、急な事態にも落ち着いて対応しやすくなります。失敗例としては、火葬場の空きが無く日程が大幅にずれてしまうケースや、関係者への連絡が遅れ混乱が生じることが挙げられます。
最近では「一日葬」など負担軽減を重視した形式も増えており、家族の希望や故人の宗教を尊重した柔軟な日取り調整が求められています。初めての方は、葬儀社に相談しながら流れを確認し、トラブルを避けるためにも早めの行動を心がけましょう。

葬儀で避けたい日や注意すべきマナーとは
葬儀の日取りを考える際、多くの方が気にするのが「六曜」や「友引」です。特に友引は「故人が友を引く」とされ、火葬や葬儀を避ける風習が根強く残っています。ただし、地域や宗教によって捉え方や重視度は異なるため、家族や関係者とよく相談することが大切です。
また、「お葬式ダメな日カレンダー」などを参考にする方もいますが、現実的には火葬場や僧侶の都合、親族のスケジュールが優先される場合も多いです。例えば、友引でも火葬場が空いていない場合や、やむを得ずその日しか日程が取れないケースもあります。迷った際は、地域の慣習や葬儀社のアドバイスを参考にしましょう。
マナー面では、親族や参列者の負担を考慮し、無理のない日程を組むことも重要です。特に高齢の方や遠方からの参列者がいる場合は、余裕を持った日取りにする配慮が求められます。トラブル回避のため、事前に十分な確認と周知を行いましょう。

親族の都合を考慮した葬儀日程の決め方
葬儀日程を決定する際、最も悩ましいのが親族のスケジュール調整です。特に遠方から来る親族や仕事の都合がある場合、全員が参列できる日を選ぶことが理想ですが、現実的には難しい場合も少なくありません。そのため、喪主やご遺族が中心となり、できるだけ多くの親族が集まりやすい日を調整しましょう。
具体的には、親族に一斉連絡を行い、候補日をいくつか提示する方法が有効です。その上で、火葬場や僧侶の予定ともすり合わせて最終決定を行います。例えば「亡くなってから葬儀まで1週間」や「平均日数」を参考に、無理のないスケジュールを組むことがポイントです。
注意点として、全員の都合を優先し過ぎると火葬場の予約が取れなくなるリスクや、故人の安置期間が長引くデメリットもあります。大切なのは、できる範囲でバランスを取りながら、家族が納得できる日程を決めることです。経験者の声として、早めに親族へ連絡し意向を確認できたことで、混乱なく日程調整できたという事例も多くあります。

葬儀日程表の使い方と注意点を押さえる
葬儀を円滑に進めるためには、「葬儀日程表」を活用して関係者全員で情報を共有することが重要です。日程表には、通夜や葬儀、火葬の時間、集合場所、僧侶や葬儀社の連絡先など、必要な情報を網羅的に記載しましょう。テンプレートを活用すると、漏れなく作成できます。
作成時の注意点は、最新の情報を反映し、変更があれば速やかに関係者へ周知することです。特に「葬儀日程表 テンプレート」を利用する場合でも、家族や親族の特別な事情や宗教的な要望があれば加筆修正が必要です。参列者が混乱しないよう、分かりやすい表現と明確なスケジュール管理を心がけましょう。
失敗例として、日程表の内容が古いまま配布され、集合時間や会場が誤って伝わったことで混乱が生じたケースもあります。特に高齢の方や遠方の親族には、電話や書面での再確認も有効です。初めて葬儀を主催する方は、葬儀社のサポートを活用しながら日程表を作成すると安心です。

火葬場や僧侶の予定と葬儀日程調整の方法
葬儀日程を決めるうえで最も現実的な制約となるのが、火葬場と僧侶の予定です。特に火葬場は地域によって混雑状況が大きく異なり、希望日に予約が取れないことも珍しくありません。まずは逝去後できるだけ早く火葬場の空き状況を確認し、希望日を仮押さえすることが大切です。
僧侶の都合も、法要や他の葬儀と重なる場合があるため、早めに打診しましょう。菩提寺がある場合は、寺院の慣習や他家の予定も考慮する必要があります。調整の際は、候補日を複数用意しておくとスムーズです。もし希望日に調整できない場合は、親族や関係者へ事情を説明し、理解を得ることがポイントです。
実際の現場では「火葬場の空きが1週間後しかなかった」「僧侶の都合で日程をずらした」などの事例も見られます。こうした場合でも、家族や参列者が納得できるよう丁寧な説明と調整が必要です。初めての方や不安な方は、葬儀社が調整を代行してくれるサービスを利用するのもおすすめです。
六曜や友引が気になる葬儀スケジュール調整法

六曜と友引を踏まえた葬儀日程調整の基礎
葬儀の日程を決める際、多くの方が気にされるのが六曜や友引といった暦上の「日の良し悪し」です。六曜とは大安・友引・先勝・先負・赤口・仏滅の6つを指し、特に「友引」は葬儀を避ける日として広く知られています。これは「友を引く」という言葉の響きから、縁起を担ぐ風習が根付いたためです。
ただし、六曜の考え方は地域や宗教、家族の意向によっても重視度が異なります。最近では火葬場や式場の空き状況、親族のスケジュール調整が優先されるケースも増えています。六曜を重視する場合は、菩提寺やご親族と事前に相談し、トラブルを避けることが大切です。
実際に「友引」に当たる日を避けて日程を決めたことで、親族間の納得感が得られた例もあれば、仕事や遠方からの参列者の都合を優先して六曜にこだわらず執り行ったケースもあります。最終的には故人や遺族の意向を尊重しつつ、柔軟に判断することが求められます。

葬儀スケジュール調整時の注意ポイント
葬儀の日程調整では、六曜以外にも押さえるべき現実的なポイントがあります。まず、火葬場や葬儀式場の空き状況を早めに確認することが重要です。特に大都市圏では希望日時がすぐに埋まることも多く、迅速な連絡と予約が求められます。
また、親族や参列者の都合、僧侶や宗教者のスケジュールも調整の対象となります。遠方からの移動や仕事の都合を考慮し、無理のない日取りを設定しましょう。加えて、法要の流れや地域ごとの慣習も確認しておくと安心です。
トラブル防止のためには、日程決定後すぐに関係者へ連絡し、誤解や行き違いが生じないようにしましょう。葬儀日程表やテンプレートを活用して、情報共有を徹底することが円滑な進行につながります。

お葬式ダメな日カレンダーの活用方法
「お葬式ダメな日カレンダー」は、六曜や友引、宗教行事など葬儀を避けるべき日をまとめた便利なツールです。カレンダーを参考にすることで、日取り選びの際に迷いが生じにくくなります。特に2025年版など最新情報を確認することが重要です。
ただし、カレンダーに記載されている「ダメな日」は、あくまで伝統的な観点や慣習に基づく目安です。現実には火葬場の混雑状況や家族の都合が優先される場合も多く、全てを守る必要はありません。周囲の意見や地域の風習と照らし合わせて柔軟に利用しましょう。
利用時の注意点として、カレンダーだけに頼らず、菩提寺や葬儀社と相談のうえ最終決定することが大切です。家族や関係者の納得感を高めるためにも、複数の情報源を活用し、バランスの取れた判断を心がけましょう。

友引に葬儀を避けるべき理由と対策案
友引が葬儀で避けられる主な理由は、「友を引く」という言葉の響きが、参列者や大切な人に不幸が及ぶことを連想させるためです。特に高齢者や伝統を重んじる家族では、友引の日の葬儀を強く避ける傾向があります。
しかし、現代では火葬場や式場の予約状況、親族のスケジュールなど現実的な事情から、友引に葬儀を行わざるを得ないケースも見られます。その場合、通夜や告別式は友引に行い、火葬は翌日以降にずらすなどの対策が一般的です。
また、地域や宗派によっては「友引人形」を棺に添えることで厄除けとする風習もあります。友引に葬儀を行う場合は、菩提寺や葬儀社と相談し、適切な対応を取ることが大切です。事前に親族へ説明し、誤解や不安を解消する配慮も忘れないようにしましょう。

葬儀日程 聞き方例文と伝え方のマナー
葬儀日程を親族や関係者に確認する際は、相手の気持ちに配慮した丁寧な聞き方が求められます。たとえば「ご都合の良いお日にちはございますか」「ご希望される日取りがあればお知らせください」などの表現が一般的です。
伝え方のマナーとしては、日程が決まり次第速やかに連絡すること、葬儀日程表や案内状を活用し、誤解のないよう情報を正確に伝えることが重要です。電話やメール、LINEなど、相手に合わせた方法を選びましょう。
また、六曜や友引など気にされる方がいる場合は「日柄についてご配慮が必要な場合はお知らせください」と一言添えると、丁寧な印象を与えます。急な連絡となることも多いため、相手の負担を最小限にする気遣いが大切です。
親族の都合を踏まえた葬儀の日程決定術

葬儀で親族の都合を調整する具体的な方法
葬儀の日取りを決める際、まず大切なのは親族の都合をできるだけ尊重することです。近親者の多くが遠方から参列する場合や、仕事の都合で日程調整が必要な場合も少なくありません。
そのため、訃報を伝えた段階で主要な親族のスケジュールを確認し、候補日をいくつか挙げて調整を始めるのが基本です。
具体的な方法としては、連絡網やグループチャットを活用して意見を集約する、喪主や遺族代表が中心となって全員の都合を聞き取るなどが挙げられます。
また、火葬場や式場の空き状況を事前に調べたうえで候補日を絞り込むことも重要です。
注意点として、地域や宗教による慣習、例えば六曜(友引など)や「お葬式ダメな日カレンダー」を参考にする家庭もありますので、親族それぞれの価値観を尊重した話し合いが求められます。
最終的には、全員が納得できる形に落とし込むことが円滑な葬儀運営のカギとなります。

親族間の意見調整と葬儀日取り決定の実践
葬儀の日程を決める際、親族間で意見が分かれることは少なくありません。例えば「友引は避けたい」「仕事の都合で平日は難しい」など、さまざまな要望が出ることが一般的です。
このような場合、まずは各意見の理由を丁寧に聞き取り、全体の希望を整理することが重要です。
実践的な調整方法としては、候補日をリスト化し、各人の希望やNG日を可視化することで合意点を探ります。
また、火葬場や式場の予約状況をもとに、現実的な日程案を提示することで、現場の事情と意向のバランスを図ることができます。
意見がまとまらない場合は、喪主や年長者が最終判断を下すことも一つの方法です。
ただし、決定後には丁寧な説明と配慮を忘れず、納得感を持ってもらうことが、親族間のトラブル防止につながります。

葬儀日程で重視すべき親族の配慮ポイント
葬儀日程を決める際、親族への配慮ポイントとして特に重視すべきなのは、遠方から参列する方の移動時間や宿泊の手配です。
また、子どもや高齢者がいる場合には、無理のない時間帯や日程選びが求められます。
さらに、親族の宗教や地域の風習によっては、六曜や友引を考慮する必要が生じます。
たとえば「友引は避けてほしい」といった要望がある際は、あらかじめカレンダーや地域の慣習を確認し、候補日を調整しましょう。
配慮が足りない場合、後から不満やトラブルにつながることもあるため、必ず事前に意見交換を行いましょう。
また、火葬場や式場の空き状況、法要や告別式の流れも踏まえたうえで、全員が納得できる日程を目指すことが大切です。

親族や関係者と円滑に日程を決めるコツ
親族や関係者と葬儀日程を円滑に決めるためには、情報共有のスピードと正確さが重要です。
まずは訃報後速やかに関係者へ一斉連絡を行い、候補日や火葬場の空き状況を把握したうえで、複数の選択肢を提示しましょう。
円滑な調整のためには、グループチャットやメールを活用して意見集約を効率化する方法が効果的です。
また、日程が決まり次第、参列者全体への早めの告知も忘れずに行うことが大切です。
葬儀社や地域の専門家に相談することで、地域特有のマナーや流れに沿ったアドバイスを受けることもできます。
失敗例として「連絡が遅れて参列できなかった」「希望が伝わらず不満が残った」などがあるため、常に丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。

葬儀のスケジュール調整で起こりやすい課題
葬儀のスケジュール調整では、火葬場や式場の予約が取りづらい、親族の予定が合わない、六曜や友引など日柄の制約がある、といった課題がよく見られます。
特に「お葬式ダメな日カレンダー」や「葬儀日程表 テンプレート」などを参考にする家庭も増えています。
また、亡くなってから葬儀までの平均日数や地域の慣習によっては、日取り調整が難航することもあります。
葬儀は一般的に数日から1週間以内に行うケースが多いですが、全員の都合や会場の空き状況によっては、調整に時間がかかることも少なくありません。
課題を解決するためには、早めの連絡と情報収集、柔軟な対応力が求められます。
また、万が一希望通りに進まない場合も想定し、代替案を用意しておくことがトラブル回避につながります。
葬儀日程表で知るマナーと避けたい日

葬儀日程表で避けるべき日とマナーの基本
葬儀の日程を決める際、多くの方が「避けるべき日」やマナーについて悩まれます。特に六曜の中でも「友引(ともびき)」は、亡くなった方が友人を引き寄せるとされ、葬儀を避ける風習が根強いです。実際、火葬場や葬儀社も友引の日は休業となることが多いため、日程選びの際は注意が必要です。
また、地域によっては「仏滅」や「大安」など六曜の吉凶にこだわるケースもありますが、最近では親族や参列者の都合、火葬場の空き状況が優先される傾向です。マナーとしては、菩提寺や親族へ早めに連絡し、意向を確認したうえで柔軟に対応することが大切です。
例えば、親族の中に遠方から駆けつける方がいる場合は、無理のない日程調整を優先し、六曜の縁起にこだわりすぎず家族の納得を重視するケースも多いです。地域や宗教の習慣も踏まえ、一律ではなく各家庭の事情に合わせて判断しましょう。

お葬式ダメな日カレンダーの見方と注意点
「お葬式ダメな日カレンダー」とは、六曜や火葬場の休業日などをまとめて確認できる便利なツールです。特に「友引」の日や年末年始など、葬儀の実施が難しい日が一目で分かるため、日取り調整の際に活用されています。近年はインターネット上でも2025年版など最新のカレンダーが簡単に入手できます。
ただし、カレンダーを参考にする際は「友引」でも地域や宗教によっては葬儀が可能な場合もあるため、必ずしも絶対ではないことに注意が必要です。カレンダーだけに頼らず、菩提寺や葬儀社、火葬場への直接確認を忘れないことがトラブル防止につながります。
例えば、火葬場の予約が難しい繁忙期や、親族の都合が合わない場合は、カレンダーの「ダメな日」以外でも日程調整が必要になることがあります。複数の情報を総合的に確認し、柔軟に対応しましょう。

葬儀日程表テンプレート活用法と実例紹介
葬儀日程表のテンプレートを活用することで、日程調整や関係者への連絡がスムーズになります。テンプレートには通夜、告別式、火葬、法要など各儀式の日時や場所を記載でき、親族や参列者に分かりやすく情報を伝えられます。特に「葬儀日程表 テンプレート」と検索することで、すぐに使えるひな形が多数見つかります。
実際の調整例として、家族葬を検討する際、親族のスケジュールや火葬場の予約状況をテンプレートにまとめて一覧化することで、混乱を防ぎやすくなります。万が一、直前で日程変更が必要になった場合も、テンプレートを修正して速やかに共有できるのが利点です。
注意点としては、日程表には六曜や友引情報も併記し、菩提寺や宗教者の意向も反映させることが重要です。テンプレートはあくまで調整のための道具として、関係者間の確認を怠らずに運用しましょう。

避けたい日を確認する葬儀マナーのポイント
葬儀の日取りを決める際、「避けたい日」を確認するのは大切なマナーの一つです。六曜では「友引」が広く避けられており、火葬場の休業日や地域の風習にも注意が必要です。加えて、宗教や宗派によっては、特定の日に葬儀を行うことが推奨されない場合もあります。
避けたい日を確認する具体的な方法としては、まず菩提寺や僧侶に相談し、宗教上の制約がないか確認します。次に、火葬場の空き状況や親族の都合をヒアリングし、調整を進めましょう。カレンダーや日程表を活用し、関係者に誤解が生じないよう情報共有することも大切です。
例えば、友引に葬儀を行うことになった場合、「友引人形」を棺に入れるなど地域独自の風習で対処するケースもあります。形式にとらわれすぎず、各家庭や地域の実情に応じて柔軟に判断することが、現代のマナーといえます。

葬儀日取りで気を付ける縁起や習慣の違い
葬儀の日取りを決める際は、六曜や友引といった縁起だけでなく、地域や宗教による習慣の違いにも配慮が必要です。たとえば、関東地方では友引を避ける傾向が強い一方、関西地方ではあまりこだわらない場合もあります。宗教によっても、仏教・神道・キリスト教などで日取りの考え方が異なります。
また、故人の信仰や家族の意向を尊重することも大切です。無理に縁起を気にしすぎて家族や親族の負担が増えたり、参列者の都合と折り合わなくなったりしないよう、バランスのとれた判断が求められます。最近は、火葬場や葬儀社の予約状況を優先するケースも増えています。
具体的には、「亡くなってから葬儀までの平均日数は3〜5日」とされますが、これは地域や家庭によって前後します。縁起や習慣にこだわりすぎず、現実的な調整と家族の納得を第一に考えることが、後悔のない葬儀につながります。
もし今日逝去した場合の葬儀の流れとは

今日亡くなった場合の葬儀準備と流れの概要
突然大切な方が亡くなった場合、まずは落ち着いて初動対応を進めることが重要です。最初に医師による死亡確認と死亡診断書の取得が必要となり、その後、葬儀社への連絡や遺体の搬送・安置を行います。家族や親族への連絡もこのタイミングで進めるのが一般的です。
葬儀の準備では、喪主や葬儀形式(一般葬・家族葬・一日葬など)の決定、会場や火葬場の予約、僧侶への依頼、参列者リストの作成といった具体的な手配が求められます。また、地域や宗教によっては菩提寺への連絡や、独自の儀式・マナーに留意する必要もあります。
時間的な余裕がない場合でも、葬儀社に相談することでスムーズな流れを確保できます。最近は24時間体制で相談できる葬儀社も多く、深夜や早朝の対応も可能です。慌てず、専門家のサポートを受けながら一つずつ準備を進めることが、失敗やトラブル防止のポイントとなります。

亡くなってから葬儀までの平均日数を解説
一般的に、亡くなってから葬儀までの平均日数は2日から5日程度とされています。これは遺族や親族の都合、火葬場や会場の空き状況、六曜(特に友引)などの日柄を考慮して日程を決めるためです。
特に都市部では火葬場の予約が混み合っており、1週間程度待つケースも珍しくありません。一方で、地域によっては翌日通夜・翌々日葬儀が一般的な場合もあり、風習や慣習が影響します。また、六曜の「友引」は避ける傾向があり、これも日程調整に関わる大きな要素です。
平均日数を把握しておくことで、参列者への連絡や式の準備に余裕を持てます。急な場合も、葬儀社に相談しながら現実的なスケジュールを組むことが大切です。

葬儀は何日かかるかスケジュールの目安
葬儀のスケジュールは、通夜と告別式を含めて2日間かかるのが一般的です。例えば、1日目に通夜、2日目に告別式と火葬を行う流れが多く見られます。家族葬や一日葬など、形式によっては1日で全てを終えるケースも増えています。
準備や手続きには、死亡届や火葬許可証の取得、会場や火葬場の予約、僧侶への依頼などが含まれます。これらの手配に最低でも1〜2日かかることが多いため、余裕を持ったスケジュール調整が必要です。
スケジュール決定時には、遺族や親族の都合、六曜や地域のマナー、火葬場の混雑状況などを総合的に考慮しましょう。特に高齢の参列者がいる場合は、移動や体調への配慮も忘れずに行うことが大切です。

通夜から葬儀までの日程調整ポイント
通夜から葬儀までの日程を調整する際は、参列者や親族のスケジュール調整が最重要ポイントです。遠方からの移動や仕事の都合を考慮し、できるだけ多くの方が参加できる日程を選びます。
また、六曜の「友引」は避ける傾向が強く、友引に当たる場合は翌日以降に葬儀・火葬をずらすのが一般的です。火葬場や会場の空き状況も早めに確認することが失敗回避のコツです。僧侶や宗教者の都合、菩提寺の予定調整も忘れずに行いましょう。
日程調整に迷った時は、葬儀社に相談して「葬儀日程表」などのテンプレートを活用するのも効果的です。マナーや地域のしきたり、現実的な都合をバランスよく考慮する姿勢が、関係者全員の納得につながります。